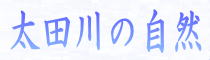鳥類
●太田川水系の生き物たち−鳥類−2006年10月 第66号
(22) モズ 〜芸北・八幡高原では1年に2回繁殖〜
モズは全長約20cmで、スズメより一回り大きい野鳥です。留鳥として、県内の農耕地や住宅地の公園、河川敷き、牧場などの開けた環境に住んでいます。
「百舌」と書いてモズと読みますが、これはモズがカワラヒワやコジュケイ、キビタキなどの小鳥のさえずりを真似て鳴くことからきています。野外で時々聞き慣れないさえずりがあると、その正体はモズが鳴いていたという経験がよくあります。
モズは頭が大きく、下へ曲がった先端にカギのある鋭いくちばしを持っており、足も頑丈で鋭い爪を持っています。この鋭いくちばしや爪を使って、昆虫やカエル、トカゲなどの小動物を捕えて餌にします。これらの小動物がいなくなる冬季には小鳥を捕えることもあり、私はスズメを捕えて枝に突き刺しているのを見たことがあります。このように小鳥でありながら獰猛な習性を持っており、「タカになったスズメ」と呼ばれることもあります。
また、カエルやトカゲ、昆虫などを有刺鉄線や尖った枝に突き刺す習性があり、これを「モズのはやにえ」と呼んでいます。はやにえの機能は「冬に備えて餌を蓄える」「なわばりを主張する」「満腹なときに余分な餌を一時的に蓄える」などが考えられていますが、それを実証する研究はまだありません。
モズの繁殖時期は早く、3月頃から始まり、4月には巣立ち雛が見られることがあります。他の小鳥の雛は主としてガ類の幼虫(毛虫や芋虫)で育てます。ガ類の幼虫がもっとも多く出現するのは6月から7月にかけてなので、育雛をこの時期に合わせています。一方、モズはカエルやバッタなどで育雛するので、4月でも十分雛を育てることが出来るのです。ところが、県内でも標高の高い北広島町の八幡高原などでは7月から8月にかけて繁殖する個体が見られます。これは「高原モズ」と呼ばれ、春に低地で繁殖した個体が高原に移動して2回目の繁殖をしていると考えられています。国内の鳥類でこのように季節によってその繁殖場所を変えて再営巣するものは知られていません。
モズは開けた環境に住んでおり、草原や牧場でも草丈が高くなるとバッタなどの餌がとれなくなります。また、八幡高原の草原では森林化が進んでおり、十年前にはたくさん繁殖していたモズも最近はめっきり減ってしまいました。
太田川の河川敷きの草原にもモズが住んでいます。これらの河川敷きも運動公園やゴルフ場などに改変され、しだいにモズが私たちの身の回りから姿を消しています。
「キィー、キィー、キィー」と「高鳴き」を聞いて秋がやってきたことを知ります。季節の風物詩であるモズがいつまでも私たちのそばにいてくれることを望みます。上野 吉雄 (写真・保井浩)