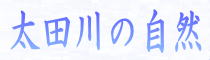サンコウチョウはオスが全長約45cmで、そのうち35cmは尾羽で占められています。メスは全長約18cmで尾羽はオスほど長くありません。その優美な姿から、英語ではパラダイス・フライキャッチャーと呼ばれています。
夏鳥として5月の中旬ごろ全国の渓流沿いのスギ、ヒノキなどの針葉樹と広葉樹の混交林に渡来し、繁殖します。近年その渡来数が全国的に減少傾向にあり心配されていますが、県内では最近少しずつ渡来数が増えているようです。
オスは「ツキ・ヒ・ホシ・ホイホイホイ」と聞きなせる声でさえずるので、月・日・星で三光鳥という名がつきました。
6月になると巣作りが始まります。巣は杉の枝や蔓などに樹皮やコケなどをクモの糸でくっつけてカップ型に造ります。
小鳥類の多くは、メスだけで巣作りを行うものが多いのですが、サンコウチョウは雌雄共同で行います。
抱卵も多くの小鳥類はメスだけが行うものが多いのですが、サンコウチョウはオスも抱卵します。オスが抱卵している時は、長い尾羽が巣から突き出しています。
雛が孵化すると雌雄共同でガ類や水生昆虫の成虫などを運び、給餌します。10〜12日で雛は巣立ちます。巣立ち後もしばらく両親から餌をもらいますが、8月頃になると雛も自立します。
このころには、シジュウカラやヤマガラ、エナガなどの混群に入っていることがあり、これらの小鳥が追い出した昆虫を捕えます。また、このような群れに入っていると、だれかがタカなどの天敵を発見して知らせてくれるというメリットもあります。また、この時期の混群にはサンコウチョウの他にセンダイムシクイやメボソムシクイなどの小鳥も入っているので要注意です。
サンコウチョウは川のそばの杉林に棲んでいることが多く、飛んでいる昆虫に跳びついて捕らえて餌にします。このような採餌方法をフライキャッチングといいます。川からはトビケラやカワゲラ、カゲロウなどの水生昆虫の成虫が沢山羽化してきます。サンコウチョウはこれらの水生昆虫を利用しているので、川のそばの林を好むのでしょう。
実際、水辺ではキビタキなどのフライキャッチングをする鳥のなわばりの大きさが森林に棲んでいるものより小さくなることが報告されています。このことは、川から陸上生物に供給される資源がとても重要であることを示しています。反対にヤマメなどの渓流魚の餌の多くは森林から落下してくる昆虫類で占められていることも良く知られています。このように、森と川とはお互いに補いながら豊かな生態系を維持し、生物の多様性を支えています。
健全な森や川を残してやれば、それにこたえてサンコウチョウやオオルリなどの夏鳥がやってきて、私たちに美しい姿やさえずりを楽しませてくれることでしょう。
|