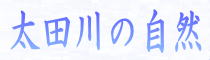|
|
|
|

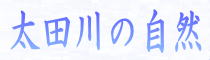
鳥類 |
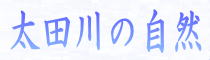 |
|
| ●太田川水系の生き物たち−鳥類−2001年7月若苗号 |
|
| (1) アカショウビン |
| 小動物豊かな広葉樹林にやってくる |
|

アカショウビンは県内では5月上旬ころに渓流沿いの良く茂った広葉樹林へ冬を越した東南アジアからやってきます。赤くて大きなくちばしや、全身の赤色はいかにも南国の鳥といった感じで、バードウォッチャーのあこがれの鳥のひとつです。警戒心が強くてなかなかその姿が見れないのですが、キョロロロ…というさえずりを聞いた人はあんがい多いと思います。 |
|
|
5月初旬に渡来すると、オスはさかんにさえずってなわばりを決めます。雨や曇りの日によくさえずるので「雨乞鳥」と呼ばれることもあります。なわばりが決まると、オスはメスのまえで翼を広げて求愛ディスプレイをはじめます。メスがオスを受け入れると巣穴掘りが始まります。私がアカショウビンを観察している芸北町の臥竜山では、ほとんどの巣穴はブナの枯れ木や枯れ枝に掘られます。場所によってはスズメバチの古巣や崖土に巣穴を掘ることもあり、キツツキの古巣を利用することもあります。巣穴を掘るのはオスで、メスは巣穴を掘っているオスのそばで見ています。そして、時々巣穴の出来具合を確かめるように巣穴をのぞきこむ行動が見られます。メスが気に入らないときはまた別の枯れ木を探して、新しく巣穴を掘らなければなりません。メスが気に入ったら産卵が始まります。
卵は1日に1個ずつ産まれ、5卵くらいになると、抱卵が始まります。抱卵は雌雄交代でおこない、メスのほうが少し長く抱卵します。抱卵開始後約20日たつとヒナが孵化します。ヒナが小さいうちはメスが抱いて温め、オスが渓流性サンショウウオの幼生やカエルなどの餌を運んできます。ヒナに羽毛が生えて体温が維持できるようになると、メスもオスといっしょに餌を運ぶようになります。育雛は約20日間で両親はその間、カエル、サンショウウオ、セミ、サワガニ、トカゲ、小魚などの餌を運び続けます。
しかし、臥竜山ではヒナが孵化してまもなくすると、テンにヒナが食べられてしまうことが多くありました。ヒナが捕食されてしまうと、また巣穴掘りからやりなおしです。そうこうしていると、ヒナが巣立つのは9月になることもあります。9月下旬には東南アジアにむけて出発しなければならないので、ヒナに旅立つための十分な体力がついているかと心配させられることもあります。
アカショウビンは餌となる小動物が数多く生息できる豊かな渓流ぞいの広葉樹林を必要とします。これは、アカショウビンのすんでいる森は多様な生物を育んでいることを示しており、いつまでもアカショウビンのすめる森を残しておきたいものです。 |
| 上野 吉雄 |
| |
|