「動態」という言葉
生態学や環境学の本を読んでいると、よく見かけるのが「動態」という言葉だ。私か現在所属している部署も「環境動態解析分野」と言う名称となっており、「動態」という言葉が含まれている。これほどに「動態」が用いられるのは、おそらく多くの人がこの分野においてこの言葉が物事を示すよい表現だと考えているからだろう。
「動態」という言葉を広辞苑で引いてみると次のように書いてある。
『動く状態。変動している状態。(例)「人口○○」。(対義語)「静態」』
「動く」という単語も、「変動」という単語も何かが変化するという意味を含んでいる。つまり「物事」がある状態からある状態へと変化することを理解するのが、「生態学」や「環境学」にとって重要であるということが言える。前号で紹介した「フロー・ストック」や「保存・非保存」の議論は「動態」を示す条件のようなものとも、捉えることが出来る。
「量」が知りたい
物事がどちらの方向(場所Aから場所Bへということもあろうし、状態Aから状態Bへということもあろう)に進んでいるのか(=動態)ということを理解することが重要であることは前号で述べた通りである。あとはその”動態”がどれくらいの頻度(確率)で起こるのか、その規模はどの程度のものなのかということに話は展開する。どちらの議論も長い話なので、今回は「規模」について考えてみることにしたい。
規模を示すにはやはり『事物』の量が知りたくなってくる。量をはかる、これを科学の世界では「定量化」という。
定量化を難しく定義すると、「一般的に質的に表現されている事物を”数値”を用いて表すこと(広辞苑より)」ということになる。実は科学の世界では似たような言葉で「定性化」というのがある。こちらの方は「性質・成分」を知ればいいということになる。つまり、「動態」自体は表現するが、それがどの程度の規模なのかは解らない。というのも対象としている現象を別の現象と比較するための「基準」がないのだから、当然規模なんて表しようがないのである。このように、他と比較できるような数値化を行うのだから「定量化」の方が「定性化」より大変な作業ともいえる。
定量化、つまり現象を表すために「数値化する」という作業をするというのは、ひたすら「測る」作業だ。この作業は重要なことで、これまでに理解されている環境問題はこれをひたすら続けているのである。空間を把握しようと思えば、あっちこっちに行ってサンプルを採ってきて分析する、時間的な経過を知りたければ、長期モニタリングを実施する。或いはこれまでに蓄積された何かを分析するということもあるかもしれない。
このようにして数値がそろえば「規模」が解ってくることになる。
測定から「原単位法」へ
測定、測定といっても限度がある。その理由はいくつかある。
まず第一に、測定にはお金も人手もかかることだ。特に最近の社会傾向として、同じことばっかりやっていると、「コスト削減」の波がやってきて、飲み込まれてしまう。このことは「定期観測」を必要とする環境分野では大きな問題となっている。
二つ目に、いくら現状を分析しても過去のことは解らないことだ。勿論、地層や氷床のように過去の記録が残るものを分析すれば解ることもある。しかし、それにはどうしてもその値が確からしいと判断する材料が必要となるわけで、地屑や氷床の試料があるからといってそう簡単に過去の環境データを復元出来るわけではない。
このようなことから、今ある情報を駆使してデータを構築することが望まれる。長年にわたってデータを蓄積しそれを分析するとなんらかの法則を見つけ出すことができる。そんなものが見つかればラッキーであるが、自然には様々な現象が複雑に絡み合っているのでそう簡単にはいかない。ここが自然科学の難しいところで、魅力的なところだ。
しかし、環境問題は緊急性を要することが多いので、そんな悠長なことはいっていられない。そこで、出てきたのが「原単位法」と呼ばれる動態を数値化する手法だ。
「原単位」とは、ある製品をつくるのにどれだけの労力、お金、材料、時間等が必要なのかをしめす量のことであり、鉱工業を中心としてよく用いられる指標である。これを逆に考えれば、単位時間単位面積単位量あたりどれだけ目的物質(例えば環境に負荷をりえる物質)が生産されるかということを調べておけば、「時間」、「面積」、「量」というような別に得られたデータを利用して目的物質の量を算出することが出来る。
架空のことを言うのは意外と難しいので、実例を出してみたい。
我々の目の前にある「瀬戸内海」は戦後、「富栄養化」という環境問題が生じたことはご存じだろう。富栄養化とは生物に必要な栄養塩(例えば、リン、窒素のような物質)が過剰に海域に供給され生物生産能力が高くなる現象のことをいう。こんな書き方をすると一見よいことのように見えるが、過剰に栄養塩が供給されるとある特定の生物だけが異常に増えたり、栄養塩が生態系のなかでうまく循環しなくなったりする。「赤潮」や「青潮」なんかがその影響の現れである。これをなんとかしようということで、どれくらいの「栄養塩」が循環しているのかを調べようとした。もちろん陸と海を連結している部分(例えば河川や海の流れ込む下水、地下水)で物質の量を計測した。しかし、この方法では部分的だし、過去のデータを復元することは難しい。そこで、「原単位法」の登場である。栄養塩がどれだけ瀬戸内海に供給されるのかを知るために、発生源を調べ、その発生源ではどれだけの栄養塩が生成されるのかを調査した。この結果は「発生負荷量等算定調査報告書(環境省)」という資料にまとめられている。概略すると、まず、発生源を生活系、産業系、その他系に分類する。それをさらに細分化して項目を設定しそれらの原単位を求める。例えば家畜一頭あたりどれだけの窒素、リンが発生するのかについて逐一導き出す。その値にその海域に属する流域における家畜の頭数を乗じることで家畜からの発生量がわかる。あとは海域に達するまでにどんな経路を経るのかということを踏まえた値を算出する。実際にはもっと複雑な作業なのだが、ここでは割愛した。
こうやって求めてみると、瀬戸内海では1979年に約700万トン/日もの窒素が流れ込んだと予想されるが、2004年には400万トン/日となっている。地域住民の努力の結果といえよう。これらは「瀬戸内海における窒素・燐の発生負荷蚩等解析調査報告書(環境省)」としてまとめられているので、興味のある方はこの資料をご覧頂きたい。
実測が出来なくても、データの蓄積によってこのように「量」を見積もることが出来るようになった。この方法は、我々地球人の最近の関心事「温暖化問題」にも活用されている。温暖化の原因物質として多くの人が取り上げるのが「二酸化炭素」だ。これは人間活動によって生じている部分が多いとみんなが考えているためだ。二酸化炭素発生量推定のためにも原単位法が用いられる。「産業連関表による二酸化炭素排出原単位」という資料が国立環境研究所から出されている。これも産業を細分化して単位活動あたりの二酸化炭素産出量がまとめられている。これによって口本がどれくらい二酸化炭素をだしているのかが推定されるわけである。
広島市のホームページには「環境家計簿」というのがダウンロードできるようになっている。これも電気・ガスなどの使用量や金額に二酸化炭素量に換算する係数を乗じることにより、我々が発生させた二酸化炭素量が解るようになっており、原単位法のひとつだといえる。
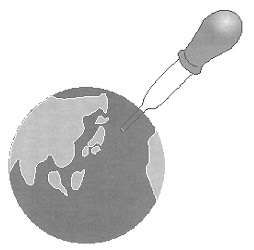 「原単位法」はこれからもどんどん活躍していきそうな気配である。しかし、原単位をどうやって設定していくか、「削減」政策をするにはどこをコントロールするのか、ほんとうに現状を表現できているのか、そのような課題は残る。「環境家計簿」をつけるのならそのような問題点を知つておくべきだ。何も知らずして、ゲームのように環境家計簿をつけるのは危険すぎる気がする。 「原単位法」はこれからもどんどん活躍していきそうな気配である。しかし、原単位をどうやって設定していくか、「削減」政策をするにはどこをコントロールするのか、ほんとうに現状を表現できているのか、そのような課題は残る。「環境家計簿」をつけるのならそのような問題点を知つておくべきだ。何も知らずして、ゲームのように環境家計簿をつけるのは危険すぎる気がする。
|
「原単位法」はこれからもどんどん活躍していきそうな気配である。しかし、原単位をどうやって設定していくか、「削減」政策をするにはどこをコントロールするのか、ほんとうに現状を表現できているのか、そのような課題は残る。「環境家計簿」をつけるのならそのような問題点を知つておくべきだ。何も知らずして、ゲームのように環境家計簿をつけるのは危険すぎる気がする。
